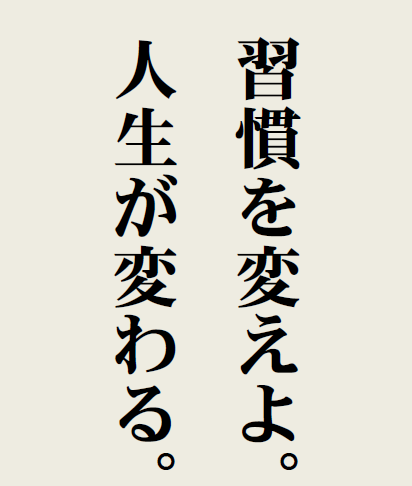前期後期制を取っている学校では定期テストがそろそろ終了していく時期になります。
テストへ向けての準備はどうだったのでしょうか?保護者の方はテスト前の生徒の姿を見て、「がんばれ」と心の中で応援をしていたことでしょう。
その応援に応えて、やるべきことをきちんと済ませ万全の準備でテストを受ける、そんな生徒もいます。
しかし、実際にはそのようなタイプはごく少数派だと思います。
多くの場合、テストから逆算しての準備がうまくできず、対策が不十分なままテストを迎えてしまったりして、結果を出せなかったりします。普段の学習をもっと自分なりに習慣づけてやっておけばよかったと思ったりします。
さらに学習状況の悪い生徒もいます。テストに出される範囲をすべて学習するどころか、出された課題を1回通りも終わらせず、テスト前日になってあわててやっていたりします。
このように、成績を上げていくために必要なことは、最近流行の言葉を借りて言えば、「習慣を変えることが9割」といっても良いのかもしれません。
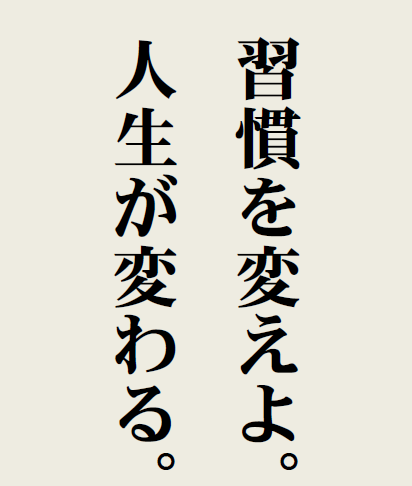
私たちは、学習習慣と勉強のやり方についての指導には特に力を入れていますが、これまでの経験からすると、学習内容面での実力向上に比べて、学習習慣の軌道修正にはかなり時間がかかることもあります。
これは、文字通り「習慣」の改善だからです。
たとえばタバコを吸う習慣のある人が、それをやめるのがなかなか大変なのと同じように、学習習慣に問題がある場合に、それを変えていくのも大変だと言えばわかりやすいかと思います。
軌道修正をするのには、①習慣を変える必要があるということを自分自身が真に思うこと、②修正にあたり自分一人でなく周りの監視下に自分を置き、後戻りできないようにすること、などが効果的ですが、実はこの①のモチベーションの点がネックになることが多いのです。
学習習慣を変えられない生徒と話をしていると、本当はこう考えているのではないかと思う時があります。
それは、「成績は上げたい。でも習慣はあまり変えたくない」という考えです。
もちろん、口頭ではそんなことは言いませんが…。
そして実は本当の問題は、さらにこの先にあります。
生徒が真に思っているのが「習慣を変えたくない」ということはもちろんのこと、むしろその前の大前提であるはずの「成績を上げたい」ということ自体を、実は本気で思ってはいない可能性があるのです。
簡単に言うと、成績が上がると嬉しいと漠然と思ってはいるものの、成績を上げたらどんないいことが待っているのかを実感できないから、本気にはなれていない、という感じでしょうか。
だから、学習習慣を長期的に変えていきたいという場合、まず将来の具体的な話をいろいろすることが効果的です。
未来のビジョンを持つことでモチベーションが変わってきたら、そこから逆算して習慣を変える必要性に自分で気づいていく生徒は多いです。
習慣を変えることが9割ですが、その9割を動かすカギは未来へのビジョンなのかも知れません。