項羽:漢の国を創設した劉邦と天下を争って敗れた楚の武将。
始皇帝で有名な秦を滅ぼすための軍を率いて大きな勢力を作り西楚の覇王を名乗った。軍事的には圧倒的に有利であったにもかかわらず、最終的には劉邦の漢に敗れてしまう。最期の時に述べられた「四面楚歌」の言葉は、現在も周囲が敵ばかりで助けがないことを表す言葉として使われている。
対照的な項羽と劉邦
「項羽と劉邦」の話は大変有名で、中学高校の古典学習では定番と言って良い程登場することが多く、アニメや映画でも繰り返し描かれているストーリーです。
歴史的史実に基づく話でその中には多くのドラマがあり、現代人の生き方にも参考となる要素をたくさん含んでおり、ご存知の方も多いのではないかと思います。
項羽は名門の出身で、ただ武勇に優れ勇猛であっただけでなく
部下に対しては優しく感情の量が大きくて、人を引きつける力を持つ武将だったと言われています。
そのため部下の統率力は非常に高く
彭城の戦いでは、劉邦の率いる56万人の連合軍にたった3万人で勝利したという記録が残っています。
驚くべき話です。
一方劉邦は、旗揚げをする時にすでに40代で、元々は地方で低い官職についていましたが、
あまりまじめに仕事もせず、不良グループとつるんで遊んだりしながら暮らしていた一庶民に過ぎませんでした。
そして旗揚げ後も劉邦は、項羽との戦いで連戦連敗を繰り返し、負けては逃げての連続でした。
そして、逃げる際には部下をののしったりして、あまり人格的に尊敬できるというようなタイプでもなかったようです。
劉邦の勝因
そんな劉邦が、なぜ最終的には項羽に勝利することができたのでしょうか?
一番の要因は、項羽が有能な部下を適正に評価できず、不公平な人事を行ったことにあるとされています。
彭越、英布、陳平といった能力のある部下たちに次々に去られ
ついには、非常に優れた宰相の范増を信じられずに追放してしまいます。
そして、最も大きな失敗は、韓信という天才軍師を用いることができなかったことです。
項羽の下では全く認めてもらえなかった韓信は、劉邦の下に走り、結局この韓信の軍事指揮能力により項羽は敗北に至ってしまったのです。
韓信は「背水の陣」の戦法を使ったことで有名な漢の軍師です。
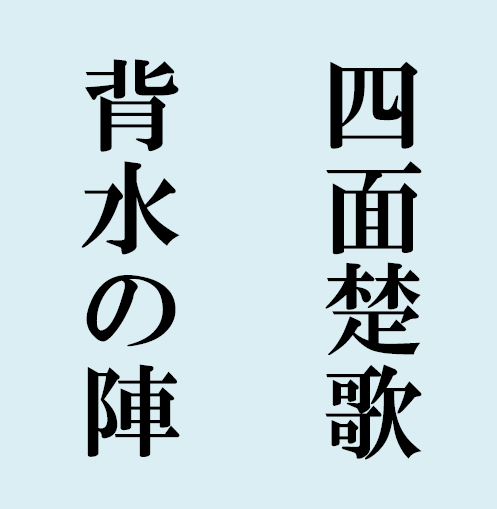
他方劉邦は、自分には高い能力がないことを知っていました。
そのため人の話を常によく聴き、能力が高い相手に対しては、本人が驚くくらいに重用をしました。
韓信が良い例で、一部の反対を押し切り、劉邦は彼を早々に大将軍にしてしまいます。
敵であったことを気にもしません。
この点あらゆる敵をすべて殲滅してしまった項羽とは好対照です。
また、彼の人事は公平でした。
論功行賞についても部下と相談して適切に行われました。
項羽のように独断で身内に有利に行うということがありませんでした。
たとえば、大将軍の1番の有力候補には、旗揚げ時から苦楽を共にしてきた義弟でもある樊噲がいましたが、劉邦は樊噲ではなく能力の高い韓信を抜擢したのです。
他にも色々な要因はあると思いますが、項羽が劉邦に勝てなかった最大の原因は、やはり公平を欠いたため、人がついてこなくなったというところにあったと思います。
人は誰でも例外なく「公平に扱われたい」という気持ちを持っています。
その気持ちを軽視すれば
いかに強大な力を持つ者も、必ず滅びる
これは歴史の必然です。
公平の重要性はどの場面でも同じ
「公平」ということは、実にさまざまな場面で要求されます。
親がその子である兄弟姉妹に接する場面
上司が部下に接する場面
教師が生徒を指導する場面等々
あるいはもっと広く
何らかの基準で選抜や補償を行う場面
政治家が国民に対して施策を行う場面等々
きちんと公平を貫けたかどうかで、その後の人間関係や世評・世論は大きく変わります。
「他人より低く見られたくない」という人の欲求を甘く考えて
不公平な扱いをして失敗をする例は、項羽の例だけでなく現代社会でも後を絶ちません。
本当に注意が必要です。
そして歴史上のどのような事例を見ても気が付くことがあります。
それは不公平な措置を行う者というのは、人の「公平というものへの切望」を綿密に考えていないという事です。
「まあ、これくらいにしておけば大丈夫だろう。こちらも金を出しているんだし」位の認識で対応を行い大失敗するという例が後を絶ちません。
最近の政治においても、不利益を受けている人の調査をしっかり行わず
「まあ、これくらい」という事でざっくりとした補償を行おうとして
信頼を大きく損なってしまったり
「世間」を知らないために、「本当に困っている人の存在にも気が付かない」
だから「公平な施策をそもそも考える事ができない」
そんな事例がたくさんあります。
「政治家だから世間を知っている」というのは大間違いで
むしろ知らない人の方が多いかも知れません。
圧力団体や声高に利益誘導を求める力のある勢力の情報を得ることが、現代の民主政治での政権維持のための基本的な運営スタイルになっているため
積極的に知ろうとしない政治家は、それ以外の国民の現実の情報をなかなか得る機会がないからです。
たとえば、無料のレジ袋がどれだけ庶民の生活に役立っていたかをご存じない方もいたりします。
仏教用語でもある「世間知」と言うのは、本来広く普遍的な「世間」の常識を知り処世の知恵を持つということであり
政治社会という限られた社会だけで通用するような処世術は、最終的には自分自身の身を滅ぼす事も多いのではないかと思います。
「世間」というのは、政治家やマスコミの人たちの生きる狭い社会ではなく
圧倒的多数の国民が現実に生きている社会全体の事です。
そこでは、皆がシビアに他人の「公平」というものに慮って、お互いを尊重し合って暮らしています。
「まあ、これくらいか」という政治家や官僚の判断でそれが一夜にして覆されてしまう、
残念ながら、そんな事例が昨今本当に多くなってきている気がします。
それでも人々は、声を上げずに一見おとなしく我慢をしているように為政者には見えるのでしょう。
でも、それが将来的にどんな不利益を為政者にもたらすのかは
項羽の例を見れば、結果を待たずしてすでに明らかではないかと思うのですが、どうでしょうか。
用心が必要ですよ。政治家諸兄。

